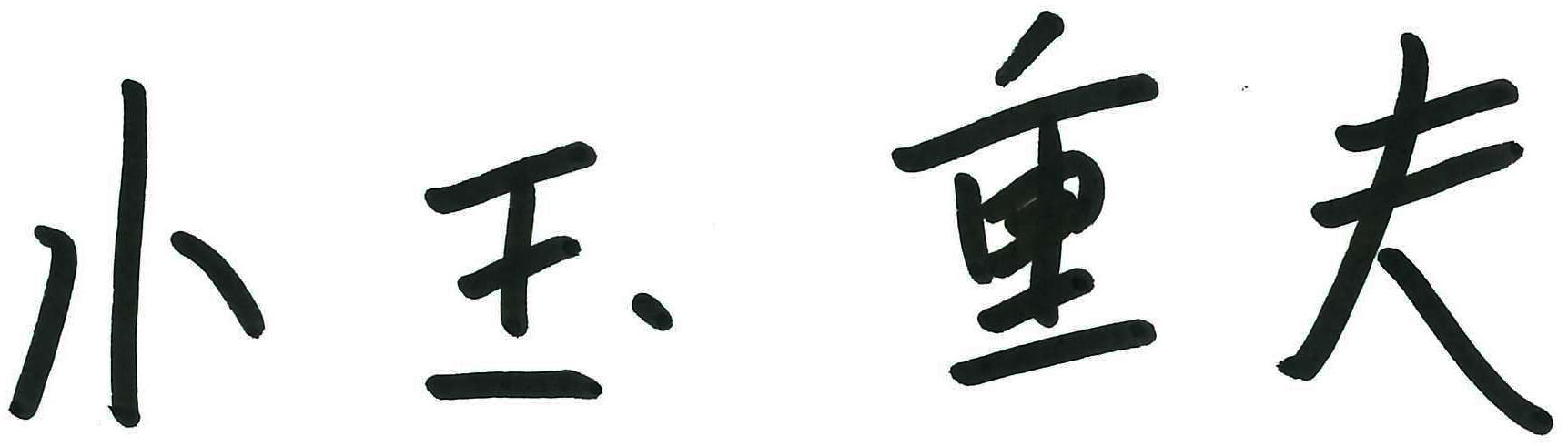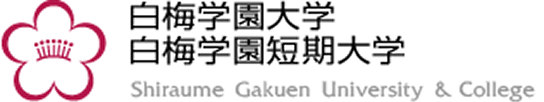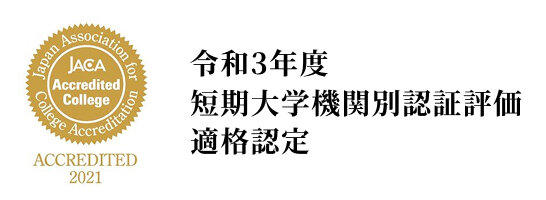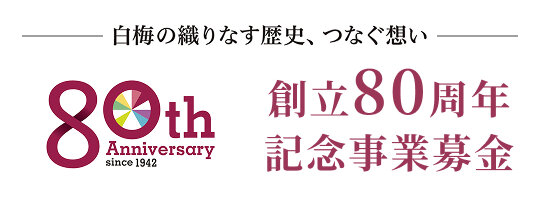学長メッセージ

白梅学園大学・白梅学園短期大学
学長 小玉 重夫
【経歴】
東京大学法学部卒。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(博士(教育学))。
慶應義塾大学助教授、お茶の水女子大学大学院教授、東京大学大学院教育学研究科教授、東京大学大学院教育学研究科長等を歴任し、2024年4月より白梅学園大学学長、白梅学園短期大学学長を併任。
学長メッセージ
ポストヒューマニズムの視点から子ども学を刷新し、時代の先端を切り拓く
白梅学園大学・短期大学はその前身から数えますと100年近くの歴史を持ち、これまで、ヒューマニズムを建学の理念として掲げ、保育、教育、福祉の領域に数を多くの人材とリーダーを輩出し、ゆるぎない地位を確保してまいりました。そうしたなか、本学は今日にいたるまで、共学の大学、短期大学として、保育、教育、福祉の業界に影響力を持ち、就職実績の高さを維持しております。
いま、世界と日本では、自然環境の破壊や、たび重なる戦争、災害、パンデミックなどで私たちの安全が脅かされています。そうした今だからこそ、本学が掲げる、人間と自然を大切にするヒューマニズムの理念はこれまで以上に重要な意味を持っています。
そうした実績のうえに立って、現在、大学と短大が取り組んでいる改革の底流をなしているのは、建学の理念であるヒューマニズムを、人間中心の価値観に安住するのではなく、私たち自身が自然の一部として自然とともに共通世界(コモンズ)をかたちづくるのだというポストヒューマニズムの視点からアップデートしていこうという先進性です。そうした観点から、私たちは、世の中の「あたりまえ」を疑う豊かな探究と学びをつくりだしていきたいと思っています。
日頃より本学の研究と教育に関心をお寄せくださる多くの皆さまに感謝を申し上げるとともに、さらなるご支援ご助力を仰ぎたく、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
白梅学園大学・白梅学園短期大学 学長